『夜をこえて、私になる』
第四章 静かなまなざし
週末の昼下がり、沙希は兄の部屋の前で立ち止まった。
「今、先輩来てるから、リビング使ってていいよ」
そう言った兄の言葉に、沙希は軽くうなずいて階段を下りる。リビングでは、兄の大学の先輩だという男性がソファに座っていた。
眼鏡をかけた穏やかな顔立ちで、文庫本を読んでいる。ふと目が合うと、彼はやわらかく笑った。
「あ、ごめんね。お邪魔してます。沙希ちゃん、だよね?」
「……はい。兄の妹です」
沙希は少しだけお辞儀をした。
そのとき、ちょうど下腹部に当てているおむつの存在を思い出して、なんともいえない居心地の悪さを感じた。
近頃咲希は、夜でもないのにおむつを穿いている。
「可愛い」、「そのままでいい」・・・友達からの言葉と共に、咲希の心には確実に深く安堵を響かせていた。
そんな風に自分のことを肯定してもらえたことに恥ずかしくも、嬉しさを感じていて、日に日におむつを穿いている自分に対しての感情が変わりつつあった。
(知られるわけないのに、なんでこんなに緊張してるんだろう……)
物静かな空間に、自分の心臓の音が身体中に鳴り響く。
本を閉じた彼が、ふと尋ねた。
「それ、いい本だね。読んだことあるよ」
テーブルの上に置いてあった沙希の小説を指さしている。思わず、沙希は頷いた。
「……はい。静かな話だけど、なんか安心するんです」
「そうだね。人には見せない弱さとか、そういうものがちゃんと描かれてるから、読んでる側も落ち着くのかも」
沙希は驚いた。自分の感じていたことと、まったく同じだった。
(この人……なんか、すごく落ち着く)
* * *
夕方、兄と先輩が帰り支度をしているときだった。
兄が部屋に忘れた書類を取りに戻り、代わりにその先輩が沙希に「少しだけ待たせてね」と言って立ち上がる。そのとき、彼の目線がふと沙希の荷物に向いた。
そこに置かれていたのは、朝のうちに鞄から出し忘れた――予備のおむつだった。
一瞬、時が止まったようだった。
沙希はとっさにそれを隠そうと手を伸ばしたが、先輩は驚くことも、笑うこともなかった。ただ、静かに目を逸らして、少しだけうつむいた。
「……ごめん。見ちゃいけないものだったよね」
「っ……違う、違うんです、それは……!」
必死に言い訳しようとする沙希に、先輩は静かに言った。
「僕、子どもの頃、長く入院してたことがあるんだ。ずっと、同じようなものを使ってた。誰にも知られたくなくて、すごくつらかった。……だから、わかるよ。そういう気持ち」
沙希は、なにも言えなかった。
その目には、同情でも興味でもない、ただただ「理解」があった。
そしてなにより――安心があった。
「もし嫌じゃなければ、今度その本の話、また聞かせてね」
それだけ言って、彼はやわらかく微笑んだ。
* * *
その夜、沙希はおむつを広げる手が、今日の出来事を思い出し少しだけ震えていた。
けれど、震えていたのは恥ずかしさではない。
誰かに知られて、しかも初めて異性に自分の秘密を知られてしまったこと、
それでも拒絶されなかったこと――そんな経験が、心をじんわりと満たしていた。
(……変だと思われなかった。ちゃんと、話を聞いてくれた)
かさ、と静かな音。
それが、今夜はどこか誇らしくすら感じられた。
・
・
・

今週?はここまでっ
さてさて咲希ちゃん、ついに男性に見つかっちゃいましたね😅
兄のパイセンあの流れで「また聞かせてね」は、本の話だけかなと疑ってしまう😛
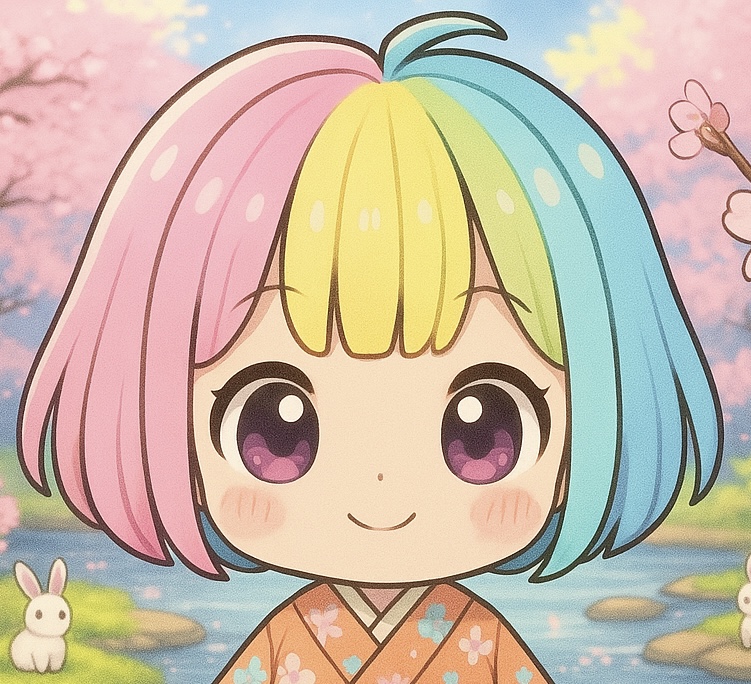
ドキドキだね。
でも、理解のある先輩で良かったー
私ならおむつのことを知ってもらえただけでも、なんだか甘えたくなっちゃう☺️
一番恥ずかしいことを知ってもらえてる安心感は、心地いいもんね😌

そうだねっ
パイセンとどうなっちゃうのかなーーー
気になるぅぅ




