『夜をこえて、私になる』
第八章 ひとりになりたい夜
春休みの夜は静かだ。
外の風の音だけが、部屋の中の時間をゆっくりと進めていた。
沙希は、机の上にノートを開いたまま、ぼんやりスマートフォンのSNSの画面を見ていた。
映っているのは、可愛い赤ちゃんの格好に身を包んだ女性の画像。淡いピンク色のおしゃぶり、ぬいぐるみの模様がついた哺乳瓶、肌着のようなロンパースパジャマ、そして不自然に大きなおしりのシルエット。
「……なんで、こんなの見てるんだろう、私」
つぶやいた声が、部屋にやさしく吸い込まれていった。
おねしょはほとんどなくなった。
それでも夜になると、おむつを履いて眠っていた。
安心する。心が落ち着く。なにより――戻ってこれる場所のように感じる。
「……赤ちゃんみたいだよね、ほんと」
それは、冷ややかな言葉ではなかった。
ただ、事実としてそう思った。
でも、そこにほんの少し、甘さと救いがあった。
(赤ちゃんって、泣いたって、ぐずったって、、もちろんおむつにおもらししちゃっても誰にも責められない)
ふと、そんな言葉が浮かんだ。
沙希はベッドに腰を下ろし、足元の引き出しから柔らかい布地のパジャマを取り出した。
ネットで注文したばかりの「子ども用ロンパース」。高校生の体には少し小さめだけれど、ストレッチ素材で優しくフィットする。
着替えてみる。
股のスナップをパチパチと留めるたびに、身体中がほぐれていくような気がした。
(誰にも見せない。ひとりきりの時間だけ)
胸元までついたスタイも、きゅっと巻いてみた。
哺乳瓶は買っていないけど、哺乳瓶に似た形の水筒を手にして、そっと口をつける。
口元が温かくて、ほっとした。
「……ああ、こういうのが欲しかったんだ、私」
それは、子どもになりたいのではなかった。
“甘えてもいい”っていう許しが、欲しかったのだ。
* * *
そのまま、枕元のノートを開く。
誰にも見せたことのないページに、細い文字でつづる。
「今日、私はおむつを履いたまま、ロンパースを着ました。
とても安心しました。
お姉さんになろうと頑張る自分も、こうして甘えたがる自分も、どちらも“私”です。
どちらかを否定しなくても、いいのかもしれないと思いました。」
ノートの上に涙が一粒、ぽとりと落ちた。
涙の意味は、もう沙希にもわからなかった。
けれどそれでよかった。
答えは、急がなくていい。
夜が、やさしく包んでくれていた。
・
・
・

ぁぁああぁぁ…
良いです…
とっても良いです
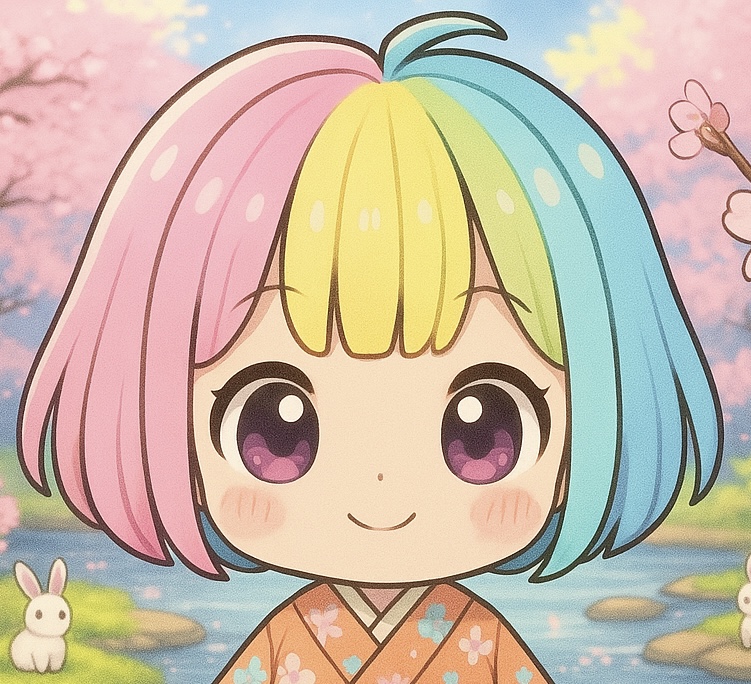
お部屋でこんな独りぼっち、ガマンできないよぉ
素敵なお世話さんと沙希ちゃんが出会えますようにっ

おひざだっこぉぉぉ
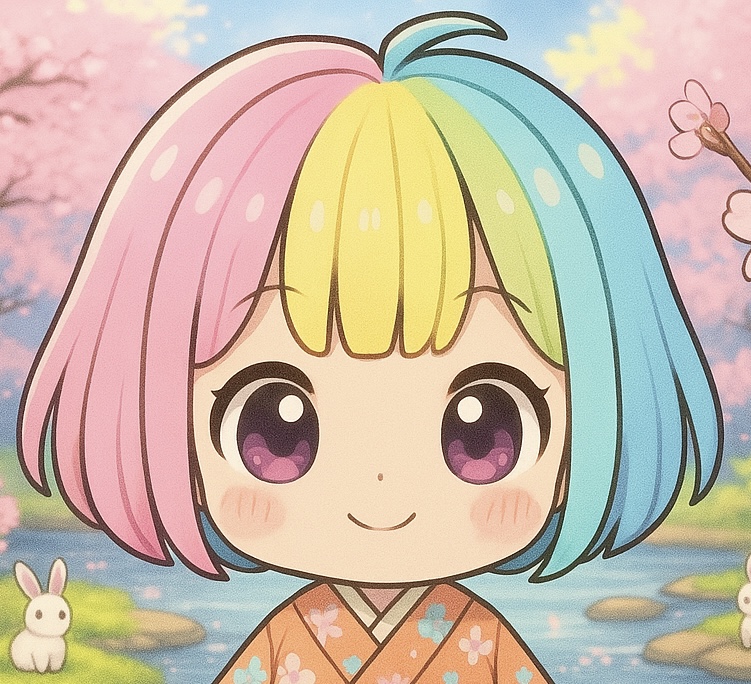
(ん…?壊れた?)

ばぶちゃんって本当にかわいいよなぁ…(語彙力なし)
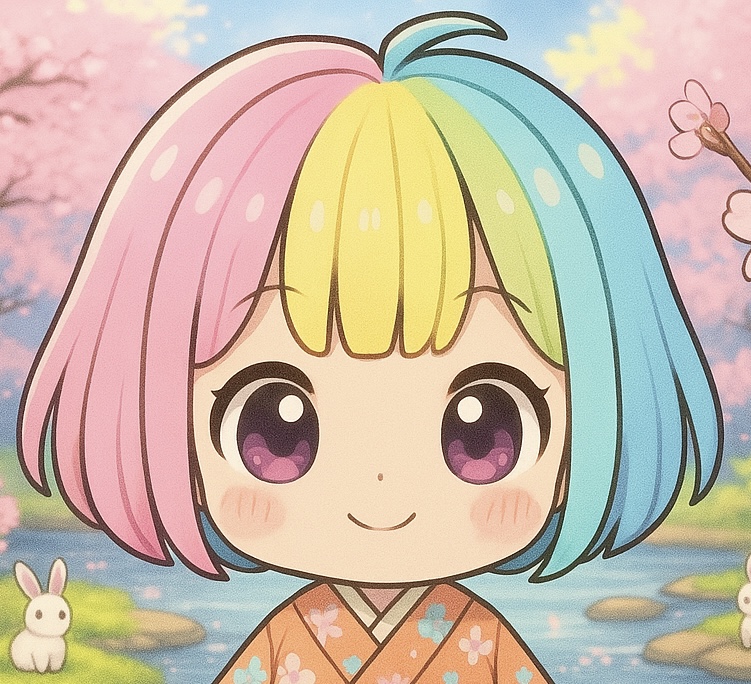
まーやが沙希ちゃんに、SNSとかで素敵なパートナーに出会えるかもしれないって、伝えてくる✨

ということは次回…
オラ、ワクワクすっぞ!




